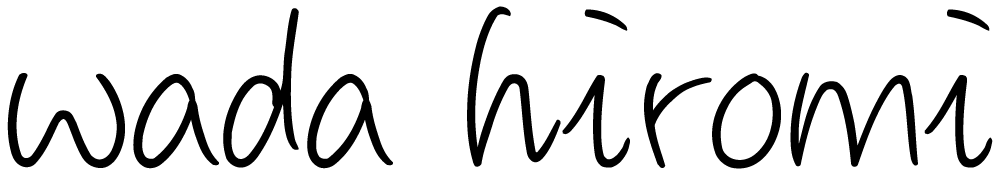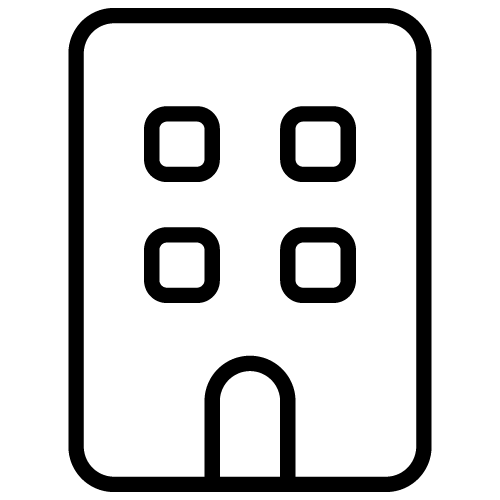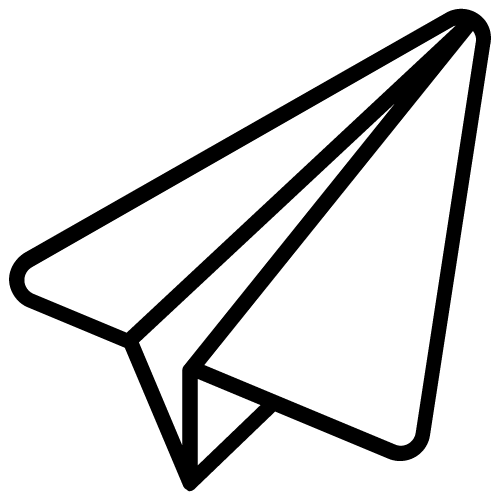多忙な職場で 「働かない人」 がいると、代わりにフォローする人の業務負荷が急増し、チームの士気もダウンします。
「結局いつも自分ばかり残業」
「注意したいのに関係が悪化しそう」
と、マネージャーもメンバーも同じ悩みを抱えがちになるでしょう。
本記事では 働かない人の心理的な原因や特徴を明確にし、そこからわかる適切な対処方法を解説します。また、イライラしてしまう時のストレスケアについてもすぐ実践できる手段を提供します。
「働かない人」の特徴
「働かない人」の主な特徴は次の9つです。
- 不平不満が多い
- 忙しいふりをしている
- 最低限の仕事しかしない(指示待ち姿勢)
- 報連相が苦手
- プライドが高い、指示に反発する
- 反省せず同じミスを繰り返す
- 向上心が低い
- 言い訳が多い
- 仕事をサボる、休憩が多い、ずる休みをする
一言でいうと「やる気がない」となりますが、問題は「なぜ、やる気がないのか?」です。理由や意味もなく仕事のやる気を出さない人はいないでしょう。単なる怠惰に見えるあの人にも、何かしら本人の中ではモチベーションを作れない理由があったりします。
不平不満が多い
いつも制度や上司に噛みつく人は、自分の努力が正しく評価されていないという“怒りの貯金”が満タンになっています。かつて成果を横取りされた記憶が傷として残り、「どうせ変わらない」と諦めた思いが、文句という形で噴き出すのです。
ランチのたびに「本社は現場を分かってない!」と机を叩く“あるある”は、単なる悪態ではなく“認められたいのに認められなかった過去の叫び”。不平を吐くたびに周囲の共感を得られると一瞬だけ承認不足の穴が埋まり、また次の不満ネタを探す。そんなループが生まれます。
忙しいふりをしている
デスクに書類を積みキーボードを打ちながら、実はメールの下書き画面で手が止まっている――彼らの目的は「やっていない」を隠すのではなく、“やれない自分”を悟られないようにする自己防衛です。過去に「遅い」「容量がない」と叱責を浴び、「助けを求めるくらいなら忙しいと見せかけろ」と脳が学習しました。
上司が通ると電話を肩に挟みメモを走らせる“あるある”は、成果より“量”で価値を測る文化が育てた保身術。その陰でブラウザには「仕事 早くなる方法」という検索履歴が残っていたりするのです。
最低限の仕事しかしない(指示待ち姿勢)
細かな指示がないと動かない人は、過去に自発的に考えて動いた結果、手痛いダメ出しを受けた経験が根深く残っています。「余計なことをするな」という無言の圧力を浴び続けると、脳は「考えるより聞いた方が安全」と配線を書き換えます。
会議で「これやっといて」と声がかかった瞬間だけキビキビ動き、ほかの時間は腕組みで待機――これは怠惰ではなく“マイナス評価を避ける最適行動”。「自分の頭で考えよう」と言われても、失敗の警報が鳴り、再び指示を待つ無限ループへ戻ってしまいます。
報連相が苦手
情報共有を避ける人は、かつて「報告したら怒られた」「相談したら無能扱いされた」という体験がトラウマになっています。「黙っていれば波風立たない」と学び、言葉を飲み込む癖が定着。進捗が遅れても黙々と抱え込み、締切直前に「実はまだです」と爆弾を落とす瞬間は、彼らの恐怖のピークです。
“開示=攻撃”とリンクしたアラートを無理やり突破した結果であり、報連相の不在は安心のコスト計算から生まれた静かなサイレンなのです。
プライドが高い・指示に反発する
強い口調で上司に噛みつく人の内側には“大きな劣等感”が潜んでいます。自分の価値を証明できる機会が少なく、外からの指示を“能力否定”と感じてしまうのです。会議で「そのやり方は浅い!」と腕を組む姿は、攻撃で自尊心を守る鎧。
新システム導入を提示され「現場を知らない人の案だ」と真っ向否定する“あるある”も、「知らないと言えない」怖さの裏返し。反発は優秀さの証明ではなく、評価されなかった過去の自分を守る必死の自己主張なのです。
反省せず同じミスを繰り返す
何度注意しても改善しない人は、“失敗=人格否定”として刷り込まれ、ミスを直視すること自体に強烈な痛みを感じます。そのため反省より先に自己防衛が起動し、事実を薄めたり忘却したりして心を守ります。
「次は大丈夫です!」と根拠なく断言するのは痛みを回避する麻酔の言葉。エクセル関数を間違え続けてもメモを取らない“あるある”は、“学び”より“恥”を避けるスイッチが優先して押されている証拠なのです。
向上心が低い
「現状で十分」と語る人は、挑戦のリターンより失敗リスクのほうが大きく見えています。幼少期に高い目標を掲げて叱責されたり、諦めムードだった環境で「背伸びは損」をインストールしました。上司が「資格を取ろう」と言っても「手当も出ないし意味ない」と涼しい顔をする“あるある”。それは怠慢ではなく、脳内のコスト計算が“挑戦=赤字”を弾き出しているからです。
だから周囲の「学ぶと世界が広がるよ」という励ましは、彼らには“投資詐欺の勧誘”に聞こえ、安全策として門を閉ざしてしまいます。
言い訳が多い
遅刻のたび電車や天気のせいにする人を責める前に、“言い訳は自尊心の救急車”という側面を思い出してください。謝罪すると自己価値が崩れる恐怖が湧き上がり、その痛みを避けるため脳が外部要因を総動員します。
幼い頃から謝る前に叱責が飛んできた人ほど、謝罪=攻撃を招くと学習。「実はPCがフリーズして」と言う“あるある”は、プライドと恐怖の綱引きが生んだ緊急避難。言い訳を口にする瞬間、本人の脳内では“自己否定センサー”が鳴り、救急回路が作動しているのです。
仕事をサボる・休憩が多い・ずる休みをする
頻繁にトイレへ立ち倉庫でスマホをいじる人は、一見怠惰に見えて“燃料切れ”を起こしている場合があります。過度なストレスや家庭問題で心のガソリンが枯渇し、「エンジンを止めないと壊れる」という本能的SOSがサボりとして噴出。月曜だけ“体調不良”で休む“あるある”も、自律神経が赤信号を点灯させた週末修理です。
休憩室で長電話をする姿は怠けではなく、「再起動に必要な冷却時間」を無意識で確保する生命維持行動。怠惰と断じる前に、燃料計がゼロを指していないか想像してみる必要があります。
「働かない人」の背景にある心理と原因

誰しも、理由もなく働かないことはありません。大なり小なり、人それぞれ背景や原因があるものです。
- 頑張りや成果が評価や給料に繋がらないと感じている
- 周囲から期待されていない、正当に評価されていないと感じる
- 仕事の目的や求められている役割が分かっていない
- 仕事そのものに価値を見出せず、生活の手段と割り切っている
- 純粋に楽をしたい、サボりたい気持ちが強い
- 目標達成後に意欲を失った
- 仕事に対する責任感が弱い
「働かない」という現象は怠惰ではなく、評価不信・目的喪失・恐れなど複数の“心のブレーキ”が同時に踏まれている状態です。そのため、エンジンを推進力に変えるにはまずブレーキの種類を特定し「外す→小さく走る→褒めて加速」という整備を施すことが不可欠。
原因を“性格”と決めつけず“環境×経験の産物”と捉え直すことで、働かない人を改善アイデアは格段に増えます。
頑張りや成果が評価や給料に繋がらないと感じている
人は「自分が注いだエネルギーがどんな形で戻ってくるか」を無意識に計算しています。幼いころのテストの点数や部活のレギュラー争いのように、頑張れば称賛が得られるという経験が薄いと、脳内には『働いても報われない』という公式が刷り込まれます。
さらに会社側が評価基準を示さないまま成果だけを求めると、努力と対価の因果関係がつかめず、脳は「リスクだけが大きい」と判断してブレーキを踏むのです。「どうせ勇気を出しても同じ」と感じる時、手を抜くことは自己防衛となり、自尊心を傷つけない鎧として機能します。
結果、挑戦するより現状維持を選ぶ方が安全だと本能的に判断してしまう。そこに“働かない”という選択の根が潜んでいます。
周囲から期待されていない、正当に評価されていないと感じる
人は誰かの「あなたならできる」という期待のまなざしで伸びる生き物です。ところが期待を示す言葉や態度が届かない環境に長くいると、『自分はいてもいなくても同じ存在』というセルフイメージが根を張ります。その状態で努力することは砂漠に水をまくような虚しさを伴い、挑戦する前に諦める癖が身につきます。
さらに、評価が曖昧だったり贔屓が公然と行われる職場では“頑張り”より“運”が支配するという不信感が強化されるため、自分のエネルギーを出し惜しみする方が合理的だという価値観が形成されます。期待値ゼロの空気は、人の可能性の芽を凍らせるのです。
仕事の目的や求められている役割が分かっていない
ゴールの見えないマラソンを走らされる感覚は、人の行動エネルギーを著しく奪います。自分の作業がどんな価値を生み、誰にバトンを渡すかという“物語”が見えなければ、タスクは単なる作業と切り離され、やりがいホルモンであるドーパミンが分泌されません。
さらに「何を優先すべきか」が不明瞭な現場では、頑張るほど方向ズレのリスクを恐れて出力を抑える方が安全だと学習します。目的の霧が濃いほど「どうせ方向修正が入る」と考え、最小の力で様子を見る戦略を本能的に選ぶ。その結果、“指示が来るまで待つ”という受動的スタイルが固定化し、自発性の芽が眠ってしまうのです。
仕事そのものに価値を見出せず、生活の手段と割り切っている
「仕事=食べるための交換券」と捉えると、投入労力は“最低投資で最大リターン”という合理的計算に収束します。幼少期に「仕事はつらいもの、休日に本当の人生がある」と聞かされて育ったり、“やりがい搾取”を経験した人ほど、自己実現を仕事に重ねることを避けがちです。
成果より拘束時間で評価する文化では「時間を売る」感覚が強固になり、「効率よくサボれたらお得」という思考回路が定着。価値の源泉を社外に置くことで心理的コストを最小化し、余剰エネルギーを趣味や副業へ振り向ける選択をする。その割り切りが“働かない”姿勢として現れます。
純粋に楽をしたい、サボりたい気持ちが強い
人間の脳は本来、エネルギー消費を抑えるようプログラムされています。現代のように情報刺激が過剰だと、脳は“決断疲れ”を避けるために省エネモードを選択しやすくなります。
加えて、過去に「手を抜いても叱られなかった」「バレても大事にならなかった」という成功体験が一度でもあると、その行動パターンは強化学習で定着。楽をすることがリスクよりリターンを上回ると判断されれば、努力はコスト高な選択肢となります。サボりは単なる怠惰ではなく、“利益最大化”という経済行動。そう脳が計算しているのです。
目標達成後に意欲を失った
ゴールテープを切ったあとの虚脱感は、マラソンランナーが味わう“燃え尽き症候群”と同じ現象です。長期にわたって放出されていたドーパミンやアドレナリンが一気に枯渇し、脳は次の報酬サイクルを見失います。しかも目標が外発的(上司の期待、数字ノルマ)だった場合、達成と同時に目的が消滅し、自分の内側に動機を再点火できません。
結果、“もう頑張らなくてもいい”という許可が下り、低空飛行が常態化。心理学ではこれを“凍結”と呼び、危険が去ったあとに過剰なエネルギー消費を避ける生存戦略と説明されます。
仕事に対する責任感が弱い
責任感とは「自分の行動が他者や組織に影響を与える」というメタ認知から生まれます。しかし、意見を否定され続けたり提案が握りつぶされた経験が重なると、『どうせ自分が関わっても結果は変わらない』という学習性無力感が形成されます。
さらに、成果と失敗の帰属を曖昧にする組織では責任が運や環境に帰されるため、自分の影響力を感じ取れません。影響力の手応えがゼロの状態では主体的に舵を握る意味がなく、責任という言葉は“他人事”に変質します。ここで見える無責任行動は、自己保護と無力感が織りなす複雑な防衛反応なのです。
「働かない人」を動かすための具体的な方法

そんな「働かない人」を動かすためには、以下の方法を試してみてください。
- 仕事に対する目標を明確に与える
- 共同作業を通じて周囲の目や協力を促す
- 責任感が必要な仕事を任せ、期待を示す
- 小さな成果でも積極的に褒め、仕事ぶりを評価する
- 1対1の対話や評価制度の見直しを検討する
- 業務効率化や柔軟な働き方制度の導入も検討する
働かない人は、自分の意思でモチベーションを作ることができません。そのため、手間はかかるかもしれませんが他のメンバーからの働きかけが必要になります。上司や先輩から指示を出すこと、同じ目線・立場のメンバーや同僚から作用させるなども有効です。
仕事に対する目標を明確に与える
目標は“数字+期限+理由”で渡すのが黄金律。「3週間で顧客満足アンケートを20件回収しよう。達成したらみんなでスイーツ会!」と掲げると、達成イメージとご褒美がドーパミンを刺激。達成後は必ず“効果の見える化”と“賞賛”で脳に成功記憶を焼き付けます。
共同作業を通じて周囲の目や協力を促す
人は“見られている効果”で行動が活性化。ホワイトボードにタスクを貼り出しペアやトリオで進捗を色分けすると、置いていかれたくない気持ちが背中を押します。「ありがとうリレー」で褒め言葉を次の人に渡す仕組みを加えると、協力と承認が同時に回り相乗効果が倍増。
責任感が必要な仕事を任せ、期待を示す
公の場で名前を載せた担当表を発表し「◯◯さん案件」と呼称すると誇りスイッチがオン。進捗を質問するたび「頼りにしてるよ」と期待のエールを添えると、責任感は荷物ではなく勲章へ変わり主体性が加速します。
小さな成果でも積極的に褒め、仕事ぶりを評価する
褒めは“内容具体・即リアルタイム・+αで感謝”が三原則。「資料の図解が分かりやすかった、5分短く説明できたよ、ありがとう!」と三拍子で称えると脳内報酬回路がフル回転。成功体験の積層が行動エネルギーの貯金になります。
1対1の対話や評価制度の見直しを検討する
月一の1on1では事実→感情→提案の順で傾聴し、評価基準の不満を吸い上げる。改善点は人事と共有し制度へ反映。「声が反映された」と感じた瞬間、信頼残高が一気に増え行動が前向きに。制度が変わる過程をオープンに見せることでさらなる協力も得られます。
業務効率化や柔軟な働き方制度の導入も検討する
RPAやテンプレート化で手作業を削減。テレワークや時差勤務で“働きやすさ”を高めれば、「忙しいふり」の余地はなくなり成果重視の文化が根づきます。空いた時間は学習や新規案件へ充当し、自己成長と組織利益が同時にアップする好循環が完成。
働かない人にイライラしない!自身のストレス対処法

それでも働かない人にイライラして収まらないときは、次のいずれかを試してみてください。
- 可能であれば物理的・精神的に距離を置く
- 割り切って気にしすぎない
- 彼らを反面教師として、自身の働きがいや成長の糧とする
- 抱えている実害を具体的に整理し、上司やメンバーに相談する
働かない人にイライラするのは損です。怒りは二次感情と言われているため、反射的にイライラする前に自身で「怒りを感じるかどうか」は実は選べるのです。
とはいえ、「イライラしないようにしよう」を決めても実行するのは難しいもの。そこで重要になるのが「気にしない」というシンプルな思考を貫くことです。
可能であれば物理的・精神的に距離を置く
席替え、担当替え、ノイズキャンセリングなど“距離のフィルター”を設置し自分の集中ゾーンを確保するのが手っ取り早い対策です。距離は逃げではなくセルフメンテナンスの手段。余白が生まれると建設的な関わり方を続ける心の体力が戻ります。
近くにいると、気にしないようにしても気になってしまうもの。そのため物理的に離れられれば良いですが、それが難しい場合が意識をもっていかれないように訓練します。「気になるから仕方がない」は厳しい言い方をすると言い訳にすぎないため、もし自分が本当に業務効率や仕事の成果を考えるのであれば、精神的な距離をとれるはずです。
割り切って気にしすぎない
変な話ですが、「気にする」から「気になる」のです。働かない人があなたにフォーカスしていないのであれば、そんな人を気にしているのはあなたの独り相撲。そう聞くと働かない人にイライラすることがなんて馬鹿らしいんだと思うでしょう。
割り切って気にしない。これが今すぐできるもっとも難易度の低い方法です。会社や社会での理不尽や思うようにいかない場面など他にもたくさんあるでしょう。すべてに向き合っていたら心が持ちません。であれば、自分がやれることに集中するのが賢い選択。働かない人はゲームの難易度調整に過ぎず、そのなかで自分ができることをやりましょう。
彼らを反面教師として、自身の働きがいや成長の糧とする
「変えられない人より自分の反応を選ぶ」と考え方を切り替えましょう。イラッと来たら「これは私の評価が上がるチャンス!」と心で呟き、感情エネルギーを行動の推進力へ転換。“陽転思考”は怒りの熱を自分のエンジンに注ぐ魔法です。
コツは「働かない人がいてよかった」に目を向けることです。物事は表裏一体なので、悪いと思ったことの裏には絶対によかったことが必ず一つは存在します。イライラという感情に支配されて、成長の糧をも逃すのは損です。
例えば、働かない人がいることで、必要最低限の仕事をしているだけでも相対的に「仕事ができる人」に見られたりもします。また、働かない人に気付けること自体が、自分がそちら側の人間はないと証明しているのもポジティブな発見でしょう。
抱えている実害を具体的に整理し、上司やメンバーに相談する
とはいえ、業務で実害が出ている場合は気にしないままとはいかないでしょう。そのような状況になってしまっていたら、抱えている実害を具体的に整理し、なるべく早く上司やメンバーに相談する必要があります。
上司やメンバーに相談する際は、「愚痴」ではなく「データ」で語りましょう。遅延回数・追加残業時間・顧客への影響を数値で示し「解決策を一緒に考えたい」と提案すれば、感情論が建設論に昇華します。上司を味方に巻き込めば組織的サポートが得られ、あなたの負担も軽減されます。
どんなことにも『よかった』は存在する

働かない人にイライラして悩んだときは、自分の将来について深く考える機会です。言い換えれば、「このタイミングで悩んでよかった」と自分を褒めてもよいということです。
どんな悪い出来事にも『よかった』は存在します。大切なのはそれに気付けるかどうかです。目標がないと悩んだことで、逆に『よかったこと』は何でしょうか。
- 仕事への価値観や人生について考えることができた
- もっと成長しなきゃとモチベーションが高まった
- 乗り越えたことで耐性ができた
- 糧としたことで前よりも精神的に強くなった
考え方次第で色んな『よかったこと』が出てきます。どんなことにも相反する事実があることを忘れないでください。もし『よかったこと』に気付けそうになければ、気付けるようになるための考え方を醸成してきましょう。もし自分一人では考え方を醸成できない人は『陽転思考』を学んでみてください。
陽転思考とは、ネガティブな事実からも「よかった」を探す思考法です。ネガティブな感情を許可し、それらを受け入れてから切り替えるという方法であり、マイナスのことを否定しません。良いとか悪いという二元論ではなく、「すべての事実はひとつですよ。見方を変えて見ましょう」という考え方であり、ビジネスにおいても重要な考え方になります。
『日刊ワダビジョン』は、陽転思考に繋がる仕事やコミュニケーションにおける本質を知れるメルマガになっていますので、この小さな一歩から皆さんの人生が前向きになることを願っています。
和田裕美の最新情報や、営業ノウハウや、好かれる話し方などの学びが無料で届きます!
メルマガにご登録いただくと
・『人生を好転させる「新・陽転思考」』の第一章
・『成約率98%の秘訣』特別ポケットブック(非売品)
のPDFをプレゼントします。
メルマガも読んでみて、ちょっと違うと思ったらすぐに解除できますので、興味のある方はぜひご登録ください。