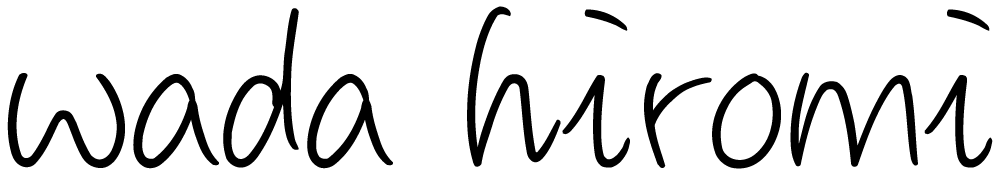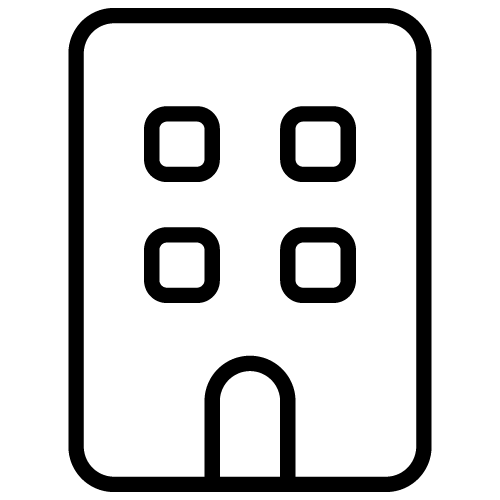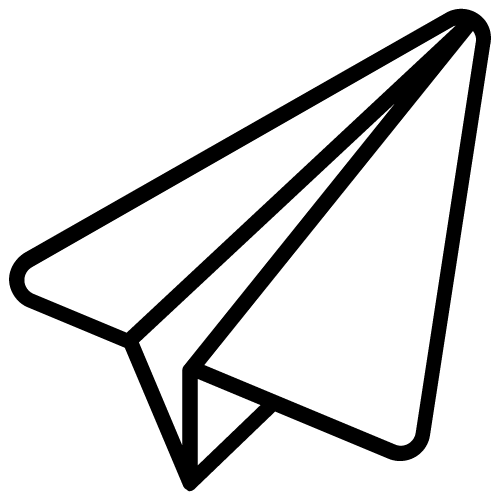あなたのまわりにも「この人、頭いいな」と感じる人物が少なからずいるでしょう。
勉強ができるからではなく、高学歴かどうかも知らない。けれど、一緒に仕事をしたりプライベートを過ごすなかで人とは違う何かを感じさせる「賢い人」には独特の雰囲気があります。
実は、そんな「頭がいい人」には共通する特徴・性格があります。
頭がいい人に共通する特徴
頭がいい人に共通する特徴、それは次の7つです。
- すぐ感情的にならない
- 自分のために周囲の人を優先する
- 自分を高く見積もらない
- ときおり非常識な面がある
- 想像力が豊か
- 食わず嫌いしない
- 好奇心が旺盛
これらを一言でまとめると、「自分の感情や感覚をコントロールするのが上手い」ということになります。頭がいいとは、賢い選択ができることです。そして賢いとは、自分を前に進めて豊かになれるよう舵を取ること。
そのために、あらゆることに考えを巡らせる能力が高いのです。
すぐ感情的にならない
野球のイチロー氏が「感情的になったら負け」と言っているように、人間は感情に動かされたときほど判断を誤ります。その多くは、怒りや悲しみという感情に意識を奪われるケースでしょう。
頭がいい人は、怒りを感じたり悲しみに暮れたりする状況でも、その感情に飲まれることはしません。今の自分の感情を一度受け止めて理解して、そのうえで「自分の頭」で考えて感情をコントロールします。
「わかっていても、いざその場面になると感情的になってしまう」という人は多いと思います。しかし、感情のコントロールは特別な勉強や資格などなくても本来誰でもできること。それができるからこそ、“頭がいい人”なのです。
自分のために周囲の人を優先する
頭がいい人は、決して人に優しいわけではありません。自分も含めて、全員にとっての最適解が何かを常に考えており、その結果として周囲の人を優先することが多いだけです。
「自分のために、自分を優先する」ことを誰しもが考えるでしょう。しかし、「自分をために、周囲の人を優先する」という一見すると反対に思える行動を整然とやってのけます。その理由は、因果は必ず巡ること、自分一人でできることには限界があることを最初から理解しているから。
人間一人ができることの限界、一方で自分という個性の重要さ、そのどちらも俯瞰して見る能力に長けていることで、周りからすると「この人は視座が違う」と感じられるのです。
自分を高く見積もらない
頭がいい人は、自分を高く見積もらない傾向があります。優れた成果を出していることが多い分、自信過剰になりがちな中でも決して自分を特別な存在とは考えません。
理由は単純で、自分を高く見積もっても得することがないからです。つい得意げになったりひけらかしたくなったり、人間の弱い部分を理解しているからこそ、自分も周囲もすべてフラットに見ることで冷静に対処する癖が付いています。
それは、課題や伸び代があることを自分に示している意味にもなり、常に成長意欲が高い状態を作れているバックボーンでもあります。
ときおり非常識な面がある
他とは違う何かを感じさせるのは、実際の考え方や行動に少なからず非常識な面があるからです。マナーは守りますが、常識には囚われず、自分の想いや考えから実態を明かすことを好むのです。
「常識」なんて誰が作ったかもわからないものに、「常識だから」という思考停止した理由では従いません。マイノリティゆえにわがままにも映りますが、本人はいたって冷静に見ています。
人と違う観点、それは疑問に感じたことを「周りがそうだからまぁいいか」では終わらせない“主体性”がある人にしか持てない感性なのです。
想像力が豊か
頭がいい人は、脳内では意外にもふざけたことをアレコレと考えていたりします。想像力が豊かで、実際には起きていないあんな事やこんな事の妄想を広げる人が多く、それが得てして未来のシミュレーションになっているのです。
常に良い想像と悪い想像を繰り広げることで、ある種のイメージトレーニングをしているような状態です。良く言えば思慮深く、他の人ならそこまで考えないようなことまで癖で考えてしまいます。
「何でも考えすぎる」という本人にとっては損な性格も、結果的には仕事ができる大きな要因になっており、普通の人の何倍も“脳内での独り言”が多いのです。
食わず嫌いしない
頭がいい人は、冷静ゆえに何でもやる前に是非を判断しがちと思うかもしれませんが、実は食わず嫌いせず「とりあえずやってみる」傾向があります。
頭がいい人は、最初から頭がいいわけではありません。どんなにすごい人も、多くの失敗や経験を重ねてきた方こその今があるだけです。つまり、頭がいい人は、他の人よりも経験値が高い場合が多く、何でも経験することに価値を置いています。
「才能があるから」や「天才だから」ではなく、人よりも苦労してきていたり、食わず嫌いせず何でもやってみる性格ゆえに多くを知っているだけなのです。
好奇心が旺盛
頭がいい人は好奇心旺盛な場合が多く、知らないことには積極的な一面を見せます。仕事ができない人や、頭が悪いと感じられる人は「知らないからやらない」と大多数の意見に賛同します。一方で、頭がいい人は「知らないからやる」と逆の考えを持っています。
これは“無謀”や考えなしなのではなく、人と同じことをしても同じ結果にしかならない、つまり一般的な平均にしかならないことを理解しているからこその行動です。
他人の意思で行動している人が、好奇心に突き動かされている人に勝つことはできません。頭がいい人は、俯瞰的に見られる視野を持つだけではなく、こういった少数派の勝ち筋を自然と掴むことができるのです。
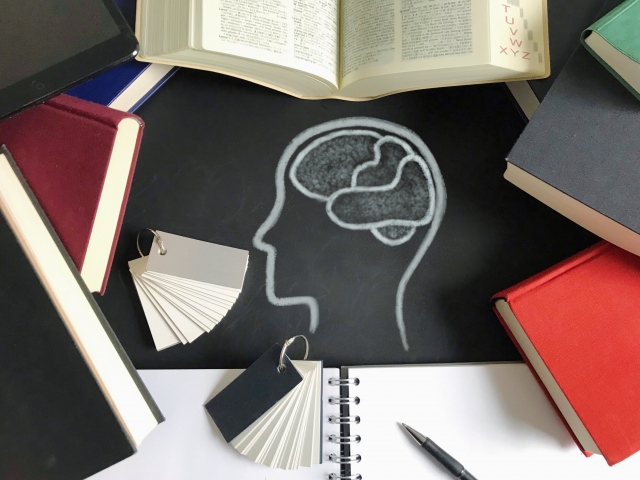
頭がいい人になるための考え方
そんな「頭がいい人」には、誰でも後天的になれます。以下のような賢い人の考え方を真似ることで、より早く近づけるでしょう。
- 話すよりも聞くことを大切にする
- 自分よりも周囲の人を大切にする
- 結果よりもプロセスを大切にする
これらによって利他主義、つまり自分の利益よりも他者の利益を優先する考え方が身に付けば、自ずと行動も変わってきて「賢い人だな」と思われる人間になっていきます。
話すよりも聞くことを大切にする
自分のことを話す=理解してもらうことよりも、人の話を聞いて理解に努めることが大切。自分をわかってもらうことで関係を築こうとするのは、相手に考えを委ねることにもなります。一方で、相手の話を傾聴して自分側が理解すれば、関係構築の舵を取りやすくなります。
また、聞き上手な人のもとには色んな人の相談や話題が飛び込みやすくなるため、知らぬ間に情報のハブ的な存在になることも。社会も会社も情報戦なので、このアドバンテージはかなり大きいでしょう。
弱い人間は、すぐ自分をわかってもらおうと自分語りばかりしてしまいます。そうではなく、聞くことに集中する強さを持って他人を理解する視野を持てるようになりましょう。
自分よりも周囲の人を大切にする
綺麗ごとではなく、自分が豊かになりたいのなら周囲の人を大切にしましょう。悪事は必ず暴かれるように、自己中心的な考えや行動は巡り廻って自分に返ってきます。逆に言えば、周囲への献身はいずれ自分に必要なタイミングで返ってくるようになっているのです。
スピリチュアルでも理想論でもなく、人同士の繋がりで構成される社会ではごく当たり前にそれが起きます。それを甘く見て、「今がよければいい」と考える人は、仕事はできても頭はよくないでしょう。未来まで見据えた行動ができていないからです。
自分の周りを見渡してみてください。「頭がいい人」に「自分さえよければいい人」はいないはずです。
結果よりもプロセスを大切にする
結果は何よりも重要ですが、それと同時にプロセスも大切にしましょう。結果だけにこだわると、次に同じ結果を出す or 避けるための再現性を図れなくなるためです。
一回の成功で、人生が順風満帆になることはほとんどなく、多くは継続的に成果を上げていかなければならないでしょう。そのために重要なのが“再現性”であり、再現性はプロセスのなかに存在します。
「なぜ上手くいったのか」だけではなく、「なぜ上手くいかなかったのか」も考えられるようになれば、失敗からも学べるようになります。

頭がいい人になるには思考の癖・考え方から変える
「頭がいい人」になりたいと願うのであれば、『陽転思考』を学んでみてください。
陽転思考とは、ネガティブな事実からも「よかった」を探す思考法です。ネガティブな感情を許可し、それらを受け入れてから切り替えるという方法であり、マイナスのことを否定しません。
良いとか悪いという二元論ではなく、「すべての事実はひとつですよ。見方を変えて見ましょう」という考え方であり、ビジネスにおいても重要な考え方になります。
『陽転思考』については、こちらのページで詳しい解説しているので是非ご覧ください。
和田裕美の最新情報や、営業ノウハウや、好かれる話し方などの学びが無料で届きます!
メルマガにご登録いただくと
・『人生を好転させる「新・陽転思考」』の第一章
・『成約率98%の秘訣』特別ポケットブック(非売品)
のPDFをプレゼントします。
メルマガも読んでみて、ちょっと違うと思ったらすぐに解除できますので、興味のある方はぜひご登録ください。