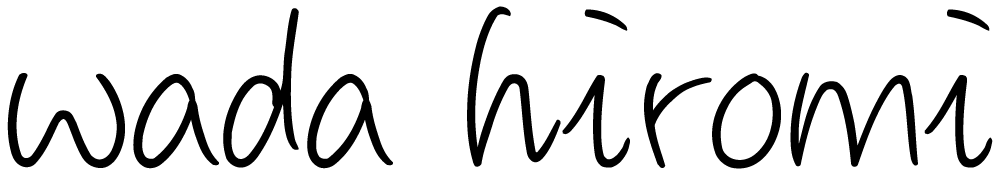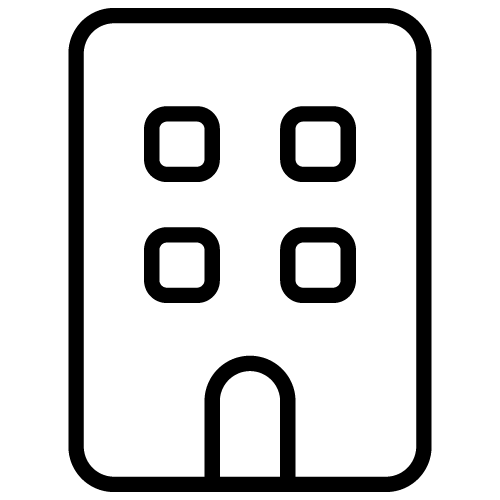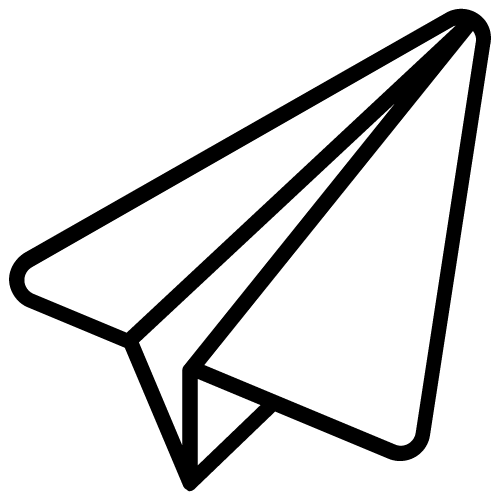50代を迎えて、若い頃のように仕事に情熱を燃やし続けることが難しくなった。
そんなふうに感じてはいませんか? かつては責任感をもって仕事に打ち込み、成果を出すためにがむしゃらに頑張ってきた。しかし、気がつけば「最低限の業務だけをこなし、終業時間を待つ」という働き方に変化しているかもしれません。
「定年まであと数年、このままでいいんだろうか?」
「もっと若い頃に戻って、仕事に打ち込めたら楽しいかもしれないのに……」と感じる方も多いでしょう。
あるいは、「十分やってきたから、これからは少しペースダウンしてもいいのでは?」と考えている方もいるかもしれません。
この記事では、50代の会社員が「静かな退職」を意識する背景や理由、そこに潜む本音を解説しながら、今後のキャリアと人生にどう向き合えばよいかを探っていきます。
「静かな退職」とは
そもそも「静かな退職」とは、欧米の一部で “Quiet Quitting” と呼ばれ始めた言葉がきっかけです。会社を退職するわけでもなく、顕著な問題行動を起こすわけでもない。
しかし、仕事に熱意を持たずに必要最低限の業務だけをこなす状態を指します。特に日本では、業務命令に背くわけでもなく淡々と仕事を続けるため、周囲から大きな非難を受けることもなく、本人も「これでいいのか」と悩みながら続けてしまうケースが目立ちます。
50代が陥りやすい「静かな退職」への流れ
若い世代の「静かな退職」は、「自分に合わない仕事はしない」「プライベートを重視したい」などの理由で生じることが多いと言われます。
一方、50代で「静かな退職」になる背景は少し異なります。たとえば、役職定年を迎えて管理職から外れたり、プロジェクトの中心を若手に譲ったりして、業務上の責任が軽くなる反面、「やりがい」を失いかねない状況が生まれます。
また、定年まで残り数年というカウントダウンが始まり、将来の見通しを冷静に考えたとき、「これ以上大きな変化は難しい」と諦めてしまうのです。
50代で課長職を数年続けたのち、役職定年で平社員に戻るケースもあるでしょう。すると、周囲からの視線も変わり、本人も「もう頑張らなくていいか」と思ってしまう。気づけば最低限の業務だけをこなすようになり、精神的には“退職”に近い感覚になることも。
単なる“働かない”ではない側面
「静かな退職」と聞くと、「仕事をサボっているの?」「会社に損害を与えるの?」とネガティブに捉える方もいるかもしれません。しかし、多くの50代が陥る「静かな退職」は、決して怠惰や無責任によるものではなく、長年働き続けたからこそ生じる疲労や諦念、価値観の変化といった要素が関わっています。
言い換えれば、「無理せずに自分のペースで仕事をしている」状態と捉えることもできるでしょう。若い頃にはキャリアアップに突き進んでいたとしても、50代はプライベートで家族の状況が変わったり、自分の健康や老後資金などを本格的に考え始めたりする時期でもあります。
その結果、以前ほど仕事に対する情熱を持てなくなり、「自分のペースで働ければいい」「大きな成果を出す必要はもうない」という考え方になりやすいです。
50代が「静かな退職」を選ぶ理由

ここでは、50代の会社員が「静かな退職 50代」の状態に陥る代表的な理由をいくつか挙げてみます。それぞれに当てはまる要素があれば、「自分だけじゃない」と安心できるかもしれません。また、複合的な要因が組み合わさっていることも。
昇進やキャリアアップへの諦め、将来への見通しのなさ
40代までの頑張りである程度の役職に就いたものの、その先の昇進がほぼ見込めないとわかったとき、人は「もうこれ以上頑張っても仕方ない」と思ってしまいがちです。特に同年代が要職に就いていたり、自分より若手がどんどん頭角を現しているのを見ると、「このまま定年まで同じポジションか……」と先のないキャリアを憂うケースも多いでしょう。
将来への不安を抱えつつ、「今さら大きなステップアップは望めない」という諦めが「静かな退職」を選ぶ一因となるわけです。
役職を外れたことによるモチベーションの低下
会社によっては、50代に達すると役職定年制度で一気に責任や権限が減ることがあります。部下を率いていた立場から急に平社員に戻り、給与もダウン。これでは「やりがいが失われる」と感じるのも自然なこと。
周囲の目も気になりつつ、「もう自分の時代は終わったんだ」と思ってしまうと、意欲を保つのが難しくなるでしょう。
仕事以外の時間を大切にしたいという価値観の変化
50代になると体力面でも衰えを感じやすくなり、健康管理の大切さを実感する方も少なくありません。また、子供が成人して自立し始めると、夫婦の時間や自分の趣味の時間を取り戻したいと考える人も増えます。
すると、「仕事第一」の姿勢が変化し、ワークライフバランス 50代を重視する方向へとシフトするのです。
長年の仕事による疲労やストレスからの解放されたい
数十年にわたって真面目に働き続けてきた結果「これ以上はもう頑張りたくない」という気持ちが芽生えるのは自然なことです。若い頃から責任感を持って走り続けてきたからこそ、50代で心身の限界を感じ、ある種の“休息モード”に入ってしまうケースは多々あります。
努力が評価されない、報われないという絶望感
会社の評価制度が曖昧であったり、上司との折り合いが悪かったりすると、どれだけ成果を出しても十分に評価されないと感じる場合があります。特に50代であれば、そのような思いを積み重ねてきた歴史が長く、「今さら改善しようがない」という諦めにつながりやすいのです。
若手とのジェネレーションギャップや新しい技術への適応疲れ
IT化やDX(デジタルトランスフォーメーション)が進むなか、常に新しい技術やシステムに対応しなければならないのは大きな負担です。
若手が当たり前のように使いこなすツールやSNSが、50代にとってはとっつきにくい場合も。ジェネレーションギャップを痛感する場面が増えれば増えるほど、「もういいかげん勉強するのも疲れた」と思ってしまうのは自然な流れかもしれません。
50代の「静かな退職」は悪いことなのか
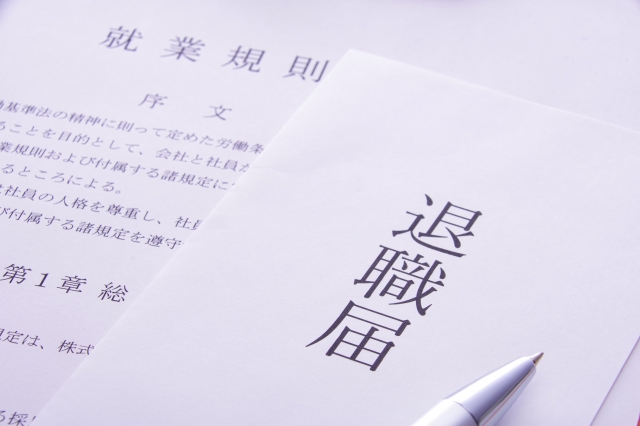
「静かな退職」には、50代の方にとって気持ちのゆとりを生み出す利点があるように見えます。長く続いた激務から距離を置くことで、心身のストレスを軽減しやすくなるからです。
また、自分のペースで仕事を進めるため、家族との時間を増やしたり、趣味や健康管理を大切にできるなど、一見すると「無理をしない」働き方のメリットを享受できるように思えます。
しかし、本当の意味で本人のためにはならないでしょう。新たな挑戦を避けてしまうことで、今後の収入や社会との繋がりを狭めてしまう可能性が高いからです。やる気を失ったまま同じポジションに留まり続けると、それ以上の成長は見込めないでしょう。結果的に、定年後の不安を増幅させてしまいます。
表面的には楽で落ち着いた選択に見える「静かな退職」ですが、実際のところは、人生死ぬまで勉強なので「そろそろ楽をしたい」と考えるのは厳しい言い方をすると“逃げ”です。「悪いこと」とは言えないものの、それを選んだ人がその先で後悔してからでは遅いのです。
50代が「静かな退職」と向き合い、自分らしく生きるために

一方で、「静かな退職」をしたからといって、自分の人生が否定されるわけではありません。むしろ、50代はこれまでの人生を振り返り、今後をどう生きるかを落ち着いて考える絶好の機会でもあります。
無理に仕事への情熱を取り戻そうとするのではなく、「自分らしく働き、生きる」ための具体的なポイントをお伝えします。
「今の自分」を受け止め、否定しない
まずは、「自分はもう頑張れない」「若い頃と比べて情熱を失った」と感じていること自体を受け止めましょう。長年働いてきたのですから、疲れを感じるのも当然です。キャリア 停滞 50代と感じるのは、頑張ってきた証でもあります。
無理に「まだまだ頑張れ!」と自分を叱咤すると、かえってストレスが増すかもしれません。大切なのは、自分が変化していることを認め、その上でどう過ごしていくかを考えることです。
変化を求めるなら、小さな一歩から
もし、「このまま静かな退職を続けるのは嫌だ」「もう少しやりがいを感じたい」という気持ちがあるなら、大きな決断を急ぐ必要はありません。転職や起業を考える50代もいますが、リスクや不安も大きいものです。
部署異動や業務変更が可能なら、上司に相談し、これまでとは違う仕事にチャレンジしてみる。責任は少し軽くても、新しいスキルを試せる場があるかもしれません。
最近は「リスキリング」という言葉が注目されていますが、50代が無理をして最新のIT技術を学ばなければならないわけではありません。むしろ、自分が興味を持てる分野をコツコツ学ぶことで、仕事にもプライベートにも良い刺激となるでしょう。
副業の可能性を探る
会社の規定や体力的な余裕によっては、副業を検討するのも一つの選択肢です。趣味を活かした小さな販売や、これまでの専門知識を活かしたコンサルなど、「お小遣い稼ぎ+やりがい」を得ることができるかもしれません。
大きな変化だけが解決策ではありません。まずは「できそう」「やってみたい」と思うことから試してみるのがコツ。仕事以外でも何かに打ち込むと、不思議と仕事への意欲が復活するケースも少なくありません。
「自分がどうありたいか」を主体的に考える
もっとも大切なのは、他人の評価や世間の目に左右されるのではなく、「自分がこの先どう生きたいか」を考えることです。たとえ静かな退職状態であっても、それがあなたにとって幸せな働き方なら問題はありません。
一方で、「本当はまだ挑戦したい」「自分の経験を若い世代に伝えたい」という想いがあるなら、どうしたら実現できるのかを真剣に考えてみましょう。
50代はまだ人生の折り返し地点とも言われます。定年まで数年あったとしても、その先には20年、30年という時間があるかもしれません。むしろこの時期に自分の将来を見据えることで、「第二の人生」をより充実させる準備ができるのです。
小さな行動を積み重ねる
いきなり大きな決断をしようとすると、リスクや周囲の反対も大きくなりがちです。興味があるイベントに出かけてみる、本を読んでみるなど、小さな行動を重ねていくうちに、自分に合った道が少しずつ見えてくることがあります。
「静かな退職」とは、決して特別なことではなく、長年頑張ってきたからこそ生じる自然な変化でもあります。無理をして仕事に打ち込み続けるよりも、一度ペースを落とし、自分の健康や趣味、家族との時間を大切にするのも立派な選択肢です。
一方で、将来的なスキルやキャリア、経済面を考えると、安易にモチベーションを捨ててしまうデメリットも否めません。
大切なのは、「自分にとって本当に大切なものは何か?」を再確認し、納得のいく選択をすること。 もしあなたが「やはりまだ挑戦したい」「仕事で得られる達成感を捨てがたい」という思いを持っているなら、焦らず少しずつ動き出す方法を探ってみましょう。逆に、「もう自分は静かな働き方で十分だ」と思えるなら、それを自分の意思で選択し、罪悪感を抱かないことが大切です。
50代は人生の成熟期でありながら、まだまだ先は長い時期でもあります。定年後にも、新たなステージが用意されているかもしれません。「静かな退職」がネガティブなものと決めつける必要はなく、あなたが主体的に選んだ働き方や生き方こそが、今後の人生を彩る大きな要素になるのです。
どうか、この時期を「もう終わり」ではなく、「これからの生き方を見直すチャンス」と捉えてみてください。焦らず、周囲と比べすぎず、「自分がどうありたいか」を問い続けながら、50代だからこそできる幸せな働き方、暮らし方を見つけていきましょう。あなたが、自分らしい生き方を確立し、心地よい毎日を過ごせるよう、心より応援しています。
どんなことにも『よかった』は存在する

自身のキャリアに悩んだときは、人生の在り方ついて深く考える機会です。言い換えれば、「このタイミングで悩んでよかった」と自分を褒めてもよいということです。
どんな悪い出来事にも『よかった』は存在します。大切なのはそれに気付けるかどうかです。目標がないと悩んだことで、逆に『よかったこと』は何でしょうか。
- 仕事への価値観や人生について考えることができた
- もっと成長しなきゃとモチベーションが高まった
- 乗り越えたことで耐性ができた
- 糧としたことで前よりも精神的に強くなった
考え方次第で色んな『よかったこと』が出てきます。どんなことにも相反する事実があることを忘れないでください。もし『よかったこと』に気付けそうになければ、気付けるようになるための考え方を醸成してきましょう。もし自分一人では考え方を醸成できない人は『陽転思考』を学んでみてください。
陽転思考とは、ネガティブな事実からも「よかった」を探す思考法です。ネガティブな感情を許可し、それらを受け入れてから切り替えるという方法であり、マイナスのことを否定しません。良いとか悪いという二元論ではなく、「すべての事実はひとつですよ。見方を変えて見ましょう」という考え方であり、ビジネスにおいても重要な考え方になります。
『日刊ワダビジョン』は、陽転思考に繋がる仕事やコミュニケーションにおける本質を知れるメルマガになっていますので、この小さな一歩から皆さんの人生が前向きになることを願っています。
和田裕美の最新情報や、営業ノウハウや、好かれる話し方などの学びが無料で届きます!
メルマガにご登録いただくと
・『人生を好転させる「新・陽転思考」』の第一章
・『成約率98%の秘訣』特別ポケットブック(非売品)
のPDFをプレゼントします。
メルマガも読んでみて、ちょっと違うと思ったらすぐに解除できますので、興味のある方はぜひご登録ください。